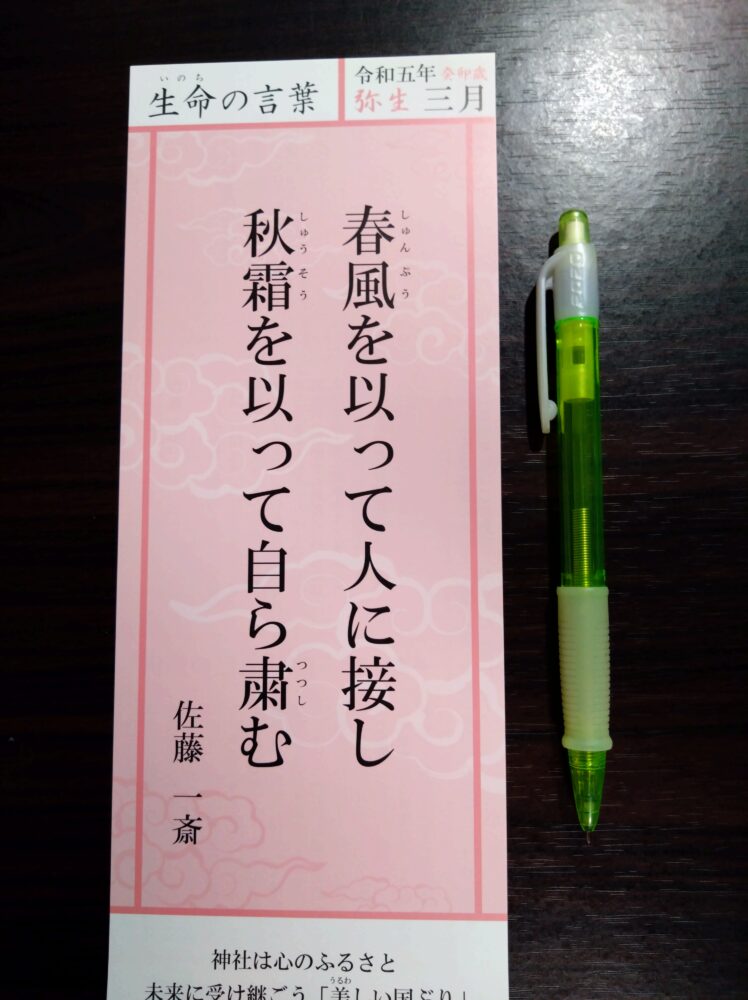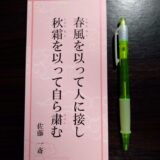ツォルキン暦
今日は、2023年3月4日(土)
Kin30
白い犬 – 青い手 音4

第一の城(赤い誕生の城):52日間の30日目
青い手(WS):13日間の04日目
——————
kin30の有名人
1907.01.23 湯川秀樹
1924.11.14 力道山
1944.10.25 黒田東彦(日銀)
1947.08.31 アニマル浜口
1964.10.05 橋本聖子
1964.10.05 横田めぐみ
1967.08.11 松村邦洋
1968.04.28 生稲晃子
1973.04.23 設楽統
1977.08.01 五代目 尾上菊之助
1997.07.12 マララ・ユスフザイ
——————
絶対反対kin
Kin160
黄色い太陽 – 赤い地球 音4
——————
鏡の向こうのもう一人の自分
Kin231
青い猿 – 白い風 音10
真面目にまっすぐ、ぐぐっと素直に。それがキーワード。
今日も楽しく、しっかり地に足をつけて生きませう。
寝起きの瞑想🙏
昨日、遅く寝たがすることができた
本町はりきゅう整骨院👍
右肩ゴリゴリ、以後、快適
読書📖
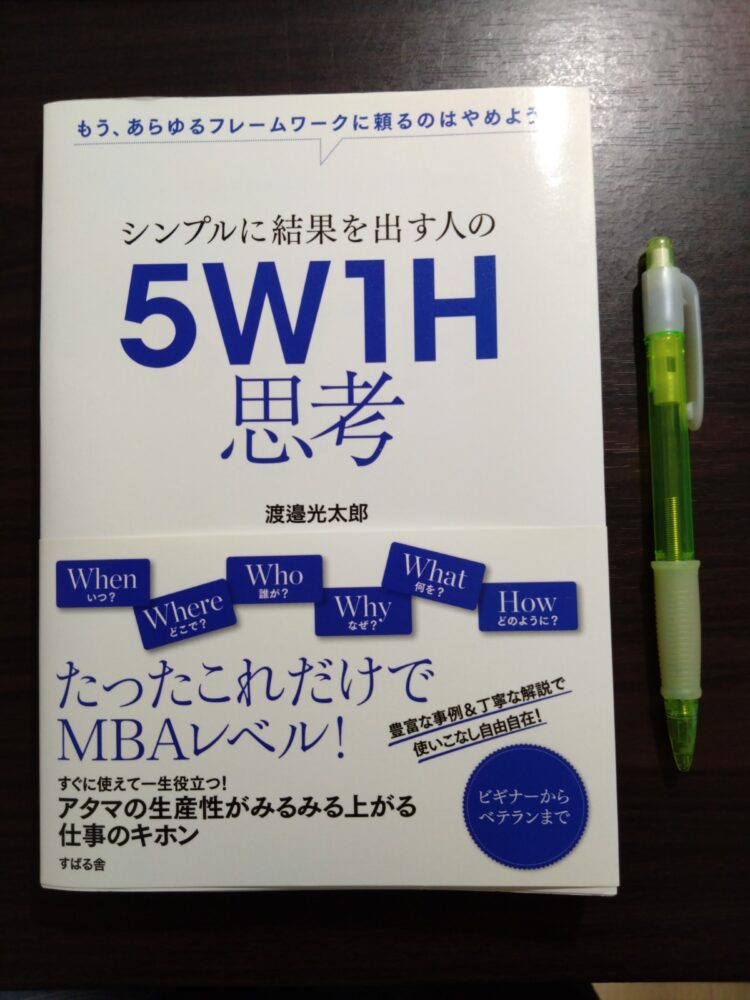
マラソン🏃

お風呂で瞑想🛀
瞼体操、眼球体操、口体操
サイドレイズ💪
20×5
思いついたWORD🗒️
チャンスは必ずやってくる!
本日のいいこと👍
⓵何をしたか(いいこと)
②楽しさ度
➡点
③反省点(楽しさ度を高めるためにどう改善するか?)
思い込みを捨てる(私もOK、あなたもOK)
第18週 第6日(土)
125 哲学 | バールーフ・スピノザ
バールーフ・スピノザ(1632~1677)は、アムステルダムのマラーノ・コミュニティーで生まれた。
マラーノとは、かつてスペインでひそかにユダヤ教を信仰していて、のちに追放された隠れユダヤ教徒のことである。
1656年、スピノザはこのユダヤ教コミュニティーから破門され、のちに名前をラテン語風なベネディクトに変えた。
そのため名前をベネディクトとする資料も多い。
◆
スピノザの哲学思想は、存命中も亡くなった後も、激しい議論を巻き起こした。
1670年、彼は『神学政治論』を刊行し、その中で、聖書は他の聖典と同じように、神ではなく人間が作った文書として解釈すべきだと訴えた。
そして、宗教にとって真に重要なのは、神の本質に関することではなく、人々が道徳的に正しいことを実践できるよう物語や教訓を通じて導くことだと主張した。
つまり、宗教とは道徳的・政治的な統制システムであり、どの宗教も、この目的を有効に果たしている限りすべて正しいとスピノザは論じたのである。
この考えは17世紀ヨーロッパでは激しい反発を招く恐れがあり、そのためスピノザは同書を匿名で出版した。
スピノザの哲学的努力の大半は、主著『エチカ』に注がれ、同書は1677年、彼がハーグで死んだ直後に出版された。
この本でスピノザは、神、自然、精神、幸福実現について体系的に 論じている。
スピノザにとって、自然の中にあるものはすべて厳密かつ必然的な因果法則によって支配されていた。
したがって、すべては必然的な法則の必然的な結果であり、いかなるものも現在の姿と異なる姿を取ることはできない。
神は自然の総体にすぎず、独立した創造者ではないと、スピノザは思っていた。
そして、世界には意味も目的もないと結論づけた。
その上でスピノザは、『エチカ』の最終部で、この結論を踏まえ、それでもどうすれば人間は幸福になれるかを考察した。
人生の大半、レンズ磨きで生計を立てていたスピノザは、1677年にハーグで亡くなった。
【豆知識】
1.スピノザがユダヤ教コミュニティーから破門された理由については確かなことは分からないが、どうやら「霊魂は不滅だ」「神は目的があって世界を創造した」という考えを否定したためらしい。
2.スピノザは、幸福状態を「至福」(beatitudo)と呼んだ。
人間として正しいか、正しくないか
島田久仁彦 国際ネゴシエーター Kunihiko Shimada
私が交渉や調停を行う際、まず心掛けているのが「とことん相手の話を聴く」ということです。
交渉のプロと聞くと、一方的に相手を捲(まく)し立てて説き伏せる、そんなイメージを持っている方がいらっしゃるかもしれません。 しかし、交渉や調停における最重要事項は、とにかく相手に喋ってもらうこと。
その中で「相手が何をあえて言わないでおこうとしているか」を探り出し、そこの本音をいかに引 き出せるか、にあります。
そのため、私はひとたび質問を投げかけるとニコニコしながら黙って聞き役に徹するようにしていました。
同時に、「相手の立場を理解し、尊重する」ことも重要なことだと思います。
戦闘地に行くと、当然交渉相手は軍服を着ています。
そこへ国連の水色のバッジを胸につけたスーツ姿の若造がやってくる。
現地の人たちがそんな人間をすぐに受け入れるか、答えはノーです。
とはいえ、仕事なのでスーツで行かざるを得ませんが、私はスーツのまま地べたにも座りますし、場合によっては「僕その服持ってないからちょうだいよ」と言って着替えたりもしました。
格好だけではありません。
軍隊のランチを一緒に食べて、ここでもとにかく相手の話を聴く。
とりわけ、この戦いに懸けている思いや祖国に残してきている家族や恋人のこと、彼らのそういう苦労話を聴いて一緒に涙を流すことも少なくありませんでした。
そうやって心底同じ目線に立って接していると、仲間意識を持ってくれるようになり、「こいつに任せたら何か状況を打開してくれるんじゃないか」と信頼を得ることができるのです。
我われ紛争調停官は、その背後に何百万人、何千万人もの人の命を預かっているのです。
自分の口先一つ、行動一つで、その人たちの命を生かしもすれば殺しもする。
だからこそ、一人でも不条理な形で傷つけたり、命を失うことがないよう、ベストを尽くす。
いかなる決断を下すか、どんな合意を取りつけるか、とことん考え抜く。
私が決断を下す上で拠(よ)りどころとしていたのは、「人間として正しいか、正しくないか」という倫理観でした。
それが私の揺るぎない信念です。
確かに、関わる案件や一緒に仕事をする相手によって、柔軟に対応していくことは大事です。
あらゆる状況をできるだけ正しく読み解いて、決定を下す。
ただ、自分自身のコアにある信念は決して曲げるべきではありません。
そして、一度出した決定は絶対に変えない。
自分が導き出したものに対してはすべての責任を負う。
それを貫き通せない人間はリーダーにはなれません。